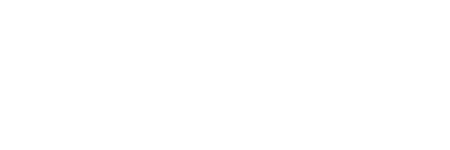湯吞みって、なんで取っ手がないんでしょうか?マグカップやティーカップなどには必ず取っ手がついているため、中の飲み物が熱くても持ちやすくて飲みやすくなりますよね。
取っ手をつける技術がなかったのでしょうか?それとも「熱いのを我慢して手に持つのが粋なんだ」みたいな江戸っ子理論でしょうか?
今回はそんな湯呑みの不思議を中心に、湯呑みの魅力や伝統工芸品についてもお話していきます。
なぜ「湯呑み」なのか

実は 「湯呑み」は正式な名称ではありません。「湯呑み」とは略称で、「湯呑み茶碗」が正確な名称となります。「湯呑み茶碗」とは読んで字の如く「湯を飲むための器」の意味です。そこから「茶碗」が省略され、「湯呑み」と呼ばれるようになったのです。
「茶碗」についても少し解説します。
今では「茶碗=ご飯を盛る器」のイメージですが、江戸時代に煎茶が流行るまで、茶碗とは字の通りお茶用の陶磁器のことを指していました。しかし時代が進むにつれ、段々とお椀の形状をした器の総称を「茶碗」と呼ぶようになると、「○○茶碗」のように頭に用途を示す単語が付くようになりました。代表的なのは「抹茶茶碗」「煎茶茶碗」そして「湯呑み茶碗」です。
ちなみに現代人の言う茶碗も正確には「飯茶碗」といいます。また、耳にすることは滅多にありませんが、「コーヒーカップ」を「珈琲茶碗」とする小説*などもあります。
* 夏目漱石『行人』、遠藤周作『月光のドミナ』など
湯呑みと市販のカップを比較
冒頭ではあたかも湯呑みに良いところがないかのように言ってしまいました。実際のところどんな違いがあるのか、湯呑みと市販のカップを比較してみましょう。
ここでいうカップとはマグカップやティーカップを指しています。
- 用途
湯呑みは日本茶を入れることを想定して作られています。
湯呑みに比べて使用頻度が高いことが考えられますので、マグカップやティーカップで日本茶を飲む方もいると思います。しかし基本的にカップは紅茶やコーヒーを入れることが想定されています。
- デザイン
冒頭で少し触れましたが、違いが一番顕著なのは「取っ手」の有無です。
マグカップやティーカップには取っ手があります。そのため熱々のままでも手に取って飲みやすいです。一方の湯呑みは取っ手がありません。そのため熱いうちは手に取って飲むことが難しく、少し冷ます必要があります。
なぜ湯呑みには取っ手がないのか

陶磁器の手触りを楽しむため
湯のみを手で持つと、自然とその陶磁器の質感を手のひらで感じることができますよね。ざらっとしていたり、つるっとしていたり。陶磁器の表面は、一様ではありません。
その質感を手のひらで感じることができるのも、湯のみに取っ手がついていないからです。マグカップやティーカップにはない魅力ですね。
温度を手のひらで確認できる
マグカップだと、熱い飲み物を入れておいても、取っ手を持って飲むから、手の熱い思いをする必要はありませんよね。でも、その反面、熱い飲み物をそのまま口に運んでしまう危険を孕んでいるとも捉えられます。
逆に、湯のみは、取っ手がないから、持ち運ぶときに、手のひらで中に入っている飲み物の温度を感じられます。手に持てないような熱さだったら、もうちょっと冷ました方がいい、ということが自ずとわかります。
ちなみに、日本茶の適温は、60〜80度なので、理にかなっていますね。
このように、一見「取っ手がない=不便」と思ってしまいがちですが、日本茶を飲むことを想定とした湯呑みはそうではありません。利便性や安全性を追求した結果、あえて取っ手がない構造であることが分かってもらえたのではないでしょうか。
日本茶の美味しい淹れ方
上述の通り、湯呑みに取っ手が無い理由の一つに、「淹れたお茶が適温になるまで冷ますため」という理由があります。この「茶を冷ます」というのは日本茶の淹れ方にも表れています。以下に簡易的な美味しいお茶の入れ方を載せますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
1.沸かした湯を直接急須に入れるのではなく、一度人数分の湯呑みに入れる
→湯の適量を測ることが出来るだけでなく、日本茶の適温まで湯を冷ますことが出来ます。
2. 急須に茶葉を入れる
3.湯呑みに入れていた湯を急須に注ぎ、1分ほど待つ。
→ここでも約1分待つことで湯を冷まします。また、極端に待ちすぎると茶葉が開きすぎてしまいます。目安1分程度にしましょう。
4.急須を3〜5回に分けて注いでいきます。分けて注ぐことでお茶の濃さが均一になります。
湯呑みの良さを堪能するなら「伝統工芸品」を!!
ここまでで湯呑みの良さを少しだけ分かっていただけたのではないでしょうか。そんな「湯呑みってちょっといいかも」と湯呑みに興味が沸いた方へ、ひとつだけお伝えしたいことがございます。
「湯呑みの良さを最大限堪能するなら伝統工芸品を選んで!」
そもそも「伝統工芸品って何?」「名前は聞くけど詳しくは知らないなぁ」という方も多いかと思います。
ここからは「伝統工芸品の魅力」そして「なぜ湯呑みを選ぶなら伝統工芸品であるべきか」ここにフォーカスして説明していきます。
伝統工芸品とは?伝統工芸品の魅力
まず伝統工芸品とは何か。伝統工芸品の定義は以下のようになっています。
- 主として日常生活の用に供されるものであること。
- その製造過程の主要部分が手工業的であること。
- 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
- 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。
(経済産業省:「伝統工芸品に関する法律について」より抜粋)
この定義に当てはまる伝統工芸品は令和4年3月時点で237品目あります。またこれとは別に、各都道府県が定めた工芸品を含めるとその数は1000品目以上に上ります。
さてそんな伝統工芸品ですが、一般的なお皿やマグカップと何が違うのでしょうか?特徴を交えながら解説していきます。
- 職人さんの手作りである
工芸品の大きな特徴はズバリこれでしょう。職人さんが長年修練を重ねて培った技術による精巧な作り。手作りだからこそ出せる味わい深い、二つとないデザインは思わずウットリしてしまいます。
また見た目にとどまらず、使いやすさも兼ね備えたデザイン性に、長年人々に愛された理由があります。
- 経年変化を楽しめる
伝統工芸品は経年変化を楽しむことができます。経年変化とは、時間とともに製品の色や性能が変わることです。使用するにつれて発生する錆ですら、良いモノになります。例えばお湯を沸かすための「鉄瓶」。多少の錆であれば、むしろ鉄分を多く含んだ白湯を毎日飲むことが出来ます。日本人の多くは鉄分不足の傾向にあるので、気になっている方は南部鉄器の鉄瓶などが大変おススメです。
- 壊れても修理して使い続けることが出来る
伝統工芸品であれば、壊れても買い替える必要はありません。
例として、「金継ぎ」と呼ばれる割れた箇所を漆などを用いて行う修理方法があります。割れた箇所に沿って金色の線が走り、オリジナルとは別の美しいデザインに生まれ変わる、大変魅力あふれる手法です。近年ではSDGsの一つとしても注目を浴びています。
湯呑みの良さはお茶を楽しめる点
では、マグカップやティーカップではなく湯呑みを選ぶ利点はどこにあるのか、なぜ湯呑みを選ぶなら伝統工芸品であるべきなのか。
その一番の理由は、「日々の一服・日々のお茶に楽しみの幅と深みが増すから」です。どういうことか。
ただ茶を飲むだけであれば、楽しめるのは茶の香り、茶の味に留まってしまいます。これが湯呑みであれば、茶の香り、茶の味に加え、「湯呑みの手触り」や「湯呑みの見た目」など、より深く、より幅広くお茶を楽しむことができます。
また先述したように、伝統工芸品であれば経年変化を楽しんだり、壊れてもオリジナルの見た目を保ったまま別の見た目を楽しむことができます。刹那の楽しみだけでなく、「時の流れを経たからこその楽しみ方」ができるのは、湯呑みの、伝統工芸品の最大の魅力であると言えるでしょう。
いきなり持っても熱くない湯呑みの紹介
熱々の日本茶が好きな方、「日本茶だけじゃなくてコーヒーや紅茶も湯呑みで飲みたいんだけど」という方もいらっしゃるかもしれません。そんな方におススメな「持っても熱くない湯呑」をいくつか紹介します。
また、今回紹介する湯呑は全て伝統工芸品に絞りました。日本の古き良き雰囲気を湯呑を通じてお楽しみ頂けるかと思います。ぜひ参考にしてください。
大堀相馬焼 松永窯 二重湯呑み(2.4寸)
大堀相馬焼は福島県双葉郡浪江町周辺で作られる陶磁器です。特徴は「青ひび」と呼ばれている美しいひび模様です。このひびは素材と釉薬(ウワグスリ)の収縮率の違いによって出来た「貫入」と呼ばれるものです。また、かつてこの地を治めていた相馬藩の御神馬が「走り駒」として描かれています。さらに大堀相馬焼は「二重焼き」という独特な器の構造をしています。そのため、入れた湯が冷めにくく、持っても熱くなりません。
萩焼 藍流組湯呑 清玩作 木箱入
萩焼は山口県萩市を中心に作られる陶磁器です。熱伝導率が少ないため、入れた湯が冷めにくく手に持った際に熱くなりにくいです。
萩焼は使い始めの頃、器の中から表面へ水漏れをします。これには萩焼に使われる土が関係しています。土の目が粗く、焼きしまりが少ないため、隙間が沢山あります。さらに表面に細かいひび(貫入)があるために、水分が表面に漏れてくるのです。
では水漏れするような湯呑をどのようにして使うのか。それは何度も使うことです。繰り返しお茶を入れることで茶渋が隙間を埋めていきます。すると段々と水漏れはしなくなり、さらに茶渋の色が湯呑に染み込むことで湯呑全体の色が変わっていきます。これは「萩の七化け」と呼ばれる、萩焼最大の特徴・魅力です。
栗久 大館 曲げわっぱ リングカップ 6色 日本製 国産 最高級 ギフト
大館曲げわっぱは秋田県大館市を中心に作られる曲げ物です。曲げ物とは、檜や杉などの薄い木の板を特殊な技法で円形・楕円形にして作る器のことをいいます。
天然の秋田杉を使用した木目と木肌の美しさが特徴的です。また軽くて持ちやすく、しっかり手入れをすれば長く使い続けることも出来ます。熱を通しにくく、結露もほとんどしないため、長時間注ぎたての温度を保つことができます。
おわりに
湯呑の魅力、伝統工芸品の魅力について説明してきました。いかがでしたでしょうか。
取っ手がない理由は「江戸っ子魂」や「技術の劣り」でもなく、思いやりやお茶を楽しむためなのだということが分かってもらえたのではないでしょうか。
この記事がきっかけとなり、日本の古き良き文化が皆様に伝われば幸いでございます。